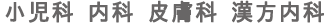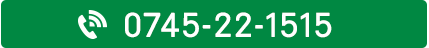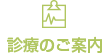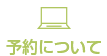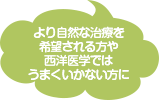お子様のどんなことでもご相談ください

「いつもとちがう!?」が、こどもの病気のサインです。
こどもは大人のように言葉で症状をうまく説明できません。大人から見て、「いつもなら○○なのに、今日は△△だなぁ」という気づきが、病気の早期発見、早期対処につながります。
ちょっと元気がない、食欲がない、寝つきが悪い、途中で起きてしまう、熱、鼻みず、鼻づまり、せき、喉の痛み、腹痛、便秘、おう吐、下痢、夜尿症(おねしょ)、ひきつけ(痙攣)、背が低い、落ち着きがないなど、お子様の体調不良や病気を幅広く診療いたします。
風邪や発熱といった、ある程度お子様がご自身の力で治せるような症状でも、自宅でのケアだけでは症状が長引いたり、悪化したりするケースもありますので、些細なことでも、遠慮無くご相談ください。
※詳しい検査や入院加療、手術などが必要な場合は周辺の地域連携病院へ、また耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科など他科にかかわる疾患の場合は、それぞれの専門医をご紹介いたします。
小外科処置もいたします
当診療所では、お子様のすり傷や切り傷の処置はもちろん、縫合を要するケガなどに対する小外科処置も行っております。

とくにケガをした後は、傷口から細菌が入ると、こじれてしまうことが多いですので、しっかりと洗浄する必要があります。また、出血は確実に止める必要があります。
受傷の様子や傷口の状態を診させていただき、適切な処置をいたします。必要に応じて、整形外科(骨折を伴う場合)、脳神経外科(頭部打撲により頭蓋内出血が疑われる場合)、形成外科(顔のケガなどで傷跡が目立つ可能性がある場合)などに紹介させていただきます。
お子様の予防接種
「痛くない」注射を心がけています。

「注射」=「痛い」というイメージが定着している子供たちは「注射は痛いから、いやだ~!」と拒んでしまいます。大人がどんなに理屈を並べても、子供たちにとって「嫌なものは嫌!」なのです。
「痛くない」注射を体験した子供たちは、理屈ではなく、体で理解してくれます。もちろん、注射する内容(予防接種の種類)によっては、より痛みを感じるものもあるので、厳密には痛みゼロにはならないわけですが、より「痛くない」注射を心がけています。
お子様の各種ワクチン接種
当診療所ではお子様の各種ワクチン接種に応じております。お取り寄せになる場合もございますので、事前に電話予約のうえ、ご来院ください。また、多種にわたる定期接種(必ず受けなくてはいけない予防接種)のスケジュールもご家族の御都合に合わせて、一緒に立てさせていただきます。卵アレルギーなどをお持ちで、ご不安な方も一度、ご相談ください。 慎重に問診や接種後観察をすることで、接種可能な場合が少なくありません。
お子様によく見られる症状
- ・熱
- ・鼻みず、鼻づまり
- ・せき、痰
- ・喉の痛み
- ・ぜーぜーする
- ・ひきつけ(痙攣)
- ・頭痛
- ・お腹が痛い
- ・おう吐、下痢
- ・便秘
- ・湿疹(ブツブツ)
- ・肌のカサつき
- ・機嫌が悪い
- ・泣き方がいつもと違う
- ・何となく元気が無い
- ・顔色が悪い
- ・食欲が無い
- ・おねしょ(夜尿症)
- ・背が低い
- ・落ち着きがない など
スムーズな診察のために
お子様の症状について、下記のような情報をお聞きしますので、ご協力いただければと思います。
診察の流れは、「問診」→「診察」(胸の音を聞く、おなかを触る、おなかの音を聞く、背中の音を聞く、のどを見る など)→「処置、処方」 となります。
- 今の症状の様子
- 症状はいつ頃から現れたのか
- 熱、せき、痰、鼻みず、喉の痛みの有無とその状態
- おしっこやうんちの状態(異常があれば、撮影してお持ちになるのも良いでしょう)
- 食欲の有無とその程度
- 症状の原因として思いあたること
- 薬に対するアレルギーの有無
- 現在、服用させている薬(お薬手帳)
- これまでに経験した大きな病気や手術
- 入院の有無 など
お子様の具合がひどく悪い場合
診療は原則として順番通りに行いますが、下記のような症状がある患者様の場合は特別な配慮をいたしますので、お申し出ください。
- 何度もおう吐を繰り返して、ぐったりしている
- ひきつけを起こしている、またはその直後である
- 激しい頭痛や腹痛がある
- 喘息の発作等により、呼吸が苦しそうである
- ウトウトして目の動きがおかしく、ぐったりしている
- 周囲の刺激に反応しない など
※このような急性症状を訴えるお子様がいらっしゃる場合には、診察の順番が前後することもありますが、あらかじめ皆様のご了承をお願いいたします。
お子様の罹りやすい病気
感染症やアレルギー性疾患など、こどもの罹りやすい代表的な疾患について、以下で説明いたします。
急性上気道炎(かぜ症候群)
上気道(鼻から喉、気管の入り口にかけての空気の通り道)に様々な病原体が感染し、この部分に炎症を起こしている状態を総称して急性上気道炎と言います。原因のほとんどはウイルスで、代表的なものにはライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルス、アデノウイルスなどがあります。
急性上気道炎の主な症状はくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、喉の痛み、せき、痰、頭痛、発熱などですが、吐き気・嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状を伴うこともあります。
鼻みずは、最初のうちは水のようにサラサラしていますが、2〜3日すると粘っこくなり、黄色みを帯びてきます。黄色みを帯びてきたからといって重症化しているわけではありません。通常は、1週間以内に症状が改善してきます。発熱の程度は様々で、熱の無いことも多いのですが、乳幼児では熱が高く(38〜40℃)、症状も全般的に強くなる傾向が見られます。
急性上気道炎の診断
通常は、特に検査は行わず、問診と診察で診断をつけます。 インフルエンザウイルスや乳幼児でのRSウイルスを疑うときは、検査をする場合があります。 お子様の状態が悪い場合(こじれているような場合)は、血液検査をして、白血球数などから体内の炎症の程度を調べることもあります。ウイルス性でなく、細菌性が疑われる場合には、喉にいる溶連菌の検査を行います。
せきが激しく、嘔吐や不眠などを伴うような場合は、気管支炎や肺炎の可能性を視野に入れて診断します。
急性上気道炎の治療
大部分はウイルス感染症のため、原則として抗生物質は使用しません。症状の程度に応じて、解熱剤や鎮咳去痰剤などを使用した対症療法を行うこともあります。水分補給や栄養補給をしっかり行い(特に乳幼児では、発熱時に水分をよく摂れないこともあるので、脱水に対する注意が大切です)、安静を保つなどのケアを行ってあげれば、ほとんどは自然に治癒します。
気管支炎
気管支の粘膜に炎症が起こった状態です。せき、鼻みず、発熱などの急性上気道炎に3〜5日遅れて発症し、激しいせき(はじめは乾いた乾性咳嗽で、しばらくすると痰の絡んだような湿性咳嗽に変化)や痰、発熱を伴います。
原因微生物の多くはウイルスで、上気道からの分泌物の下降や呼吸に随伴する吸い込み、ウイルス感染が下気道に波及することなどにより発症します。二次的な細菌感染をきたした場合は、肺炎に至ることもあります。
気管支炎の診断
気管支炎の診断は、患者さんの症状による判断、および肺炎を否定することなどによって行われます。胸部X線検査等によって、肺の状態を調べ、肺炎との鑑別をつけます。また、細菌感染が無いかを調べるためには血液検査を行います。
気管支炎の治療
ウイルスが原因の場合は、特別な治療法は無く、対症療法が中心になります。対症療法としては、鎮咳薬、去痰薬、消炎薬、気管支拡張薬などが用いられます。細菌感染が疑われる場合は、抗生物質を投与します。マイコプラズマによる場合は、ふつうの抗生物質が効かないので、マイコプラズマ用の抗生物質を処方します。
細菌感染を合併した場合を除き、多くは自然な経過のうちに治癒します。
嘔吐下痢症
嘔吐下痢症とは、ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなどのウイルスが体内に入り込み、ひどい嘔吐や下痢症状が出る病気です。熱は出ない場合が多く、出たとしても38℃前後と高熱には至らないケースがほとんどです。嘔吐や下痢は比較的短期間で治まりますが、水分が摂れない、飲水してもすぐに下痢をしてしまうなどの症状から脱水状態に至る危険があり、注意を要します。
嘔吐下痢症の原因
嘔吐下痢症の原因はウイルス感染であり、体内に侵入したウイルスを体外に追い出そうとして、嘔吐や下痢が起こります。感染するウイルスは季節によって流行する時期が異なり、秋から冬にかけてはノロウイルス、冬から春にかけてはロタウイルスといった具合ですが、最近では空調などの影響か、流行時期以外にも発症する場合も見受けられます。
なお、嘔吐下痢症はウイルス感染症であり、ほかの人にうつす危険性がありますので、嘔吐や下痢などの症状が出ている間は保育園や幼稚園、学校には行けません。特に便には、症状が治まってもしばらくはウイルスが排出されているので、油断できません。
嘔吐下痢症の症状
ウイルスに感染しても、それとは気づかないので、元気だった子どもがいきなり吐き始めたりします。嘔吐は一度では終わらずに何度も繰り返し、同時に下痢も始まります。子どもによっては嘔吐だけ、あるいは下痢だけというケースもあります。嘔吐は1日程度で治まりますが、下痢は長引きやすく、1週間くらい続くことが多いようです。便は、酸っぱいにおいのする水様状で、白色やクリーム色になります。 また、特に幼少時は食事ができないと、比較的容易に低血糖に陥ったり、そこからケトンという酸性物質が貯まり、そのせいで余計に嘔吐を繰り返すことがあります。
嘔吐下痢症の治療
吐き気止めや整腸剤、下痢止め、場合によっては抗生剤を使うこともあります。しかし、嘔吐下痢症を治すには、基本的にウイルスが体外に排出されるのを待つしかありません。子どもの状態を見守りながら、症状が治まるのを待ちましょう。少しずつ吐き気が鎮まってきたら、水分とともにおかゆなどの消化の良い食事を摂らせ、様子を見てください。食べ始めて再び吐き始めるようなことが無ければ、そのままに対応していって問題ありません。症状が重い場合は点滴を行います。
尿路感染症
尿路感染症とは、細菌による腎尿路系(腎臓・尿管・膀胱・尿道)の炎症のことで、主に膀胱の感染症(膀胱炎)、もしくは腎臓の感染症(腎盂腎炎)のことを言います。
この疾患は、尿道口(おしっこの出口)から細菌が膀胱内へと侵入することによって発症し、膀胱の中で感染がとどまっている場合は膀胱炎、細菌が膀胱から上方に上がって腎臓まで侵入すると腎盂腎炎を起こします。尿路感染症か否かは、尿の中の細菌の有無を確認することで診断をつけます。
尿路感染症の症状
赤ちゃんの尿路感染症では、発熱(38.5℃以上)、機嫌が悪い、哺乳が低下するといった全身症状だけの場合が多いようです。幼児ではお腹や背中を痛がる、おしっこをする時に痛がる、などの症状が加わる場合があります。尿がいつもより臭い、尿に血液が混じるといった症状が起きる場合もあります。学童以降の年長児ではトイレが近い、排尿時痛が強いといった排尿に伴う症状がメインになり、時には血尿も認められます。ただし、年齢を問わずに高熱を伴う場合は膀胱炎だけでなく、腎盂腎炎を発症している可能性が疑われます。
尿路感染症の診断
前記のように、尿路感染症かどうかは尿中の細菌を確認することによって診断をつけます。ただし、尿道口には普段から細菌(常在菌)が付着していて、尿の採取法によっては常在菌が尿に混ざり込んでしまい、正確な診断ができなくなる可能性があります。まだトイレに行けない乳幼児では一般に、採尿パックを尿道口に貼り付けて採尿します。年長のお子さんなら自分でおしっこを採ってもらいますが、この場合もできれば出始めの尿ではなく、途中の尿を採ってもらったほうが的確な診断に結び付きます。明らかに尿路感染症が疑われるようなケースでは、カテーテルを尿道から挿入して膀胱内の尿を直接採取したほうが確かな診断がつき、適切な治療につながります。
なお、尿中の細菌を正確に調べるには培養検査が必要なため、その日のうちには結果が出ません。そのため通常は、尿中の白血球(感染が起きると体内から尿中に出てくる)を顕微鏡で調べることによって尿路感染症の初期診断を行います。
尿路感染症の治療
発熱を伴わないような膀胱炎なら、多くの場合、抗菌薬を服用すれば丸1日で症状の改善が見られ、3日間も服用すれば完全に治ります。しかし高熱を伴い、腎盂腎炎が疑われたケースでは、2週間ほどにわたる抗菌薬の投与が必要です。最初は食欲も無く、脱水気味になっていることが多いので、点滴で抗菌薬を投与し、解熱後に食欲が出てきたら飲み薬による投与を続けます。
アトピー性皮膚炎
長引く湿疹は、アトピー性皮膚炎の可能性があります。
小児のアトピー性皮膚炎は、年齢によって皮脂の分泌量が異なるため、症状もやはり異なってきます。生後2~3ヶ月から1歳頃までのアトピー性皮膚炎では、顔や頭、耳にジクジクとした湿疹が出てきます。肘や足首などの関節部分に湿疹が生じたり、「耳切れ」と言って耳のつけ根がただれて切れてしまったりすることがあります。
2~10歳頃は手足の関節の内側や首、わきの下などにカサカサと乾燥した湿疹が出ます。また、季節の影響としては、夏場は皮膚の化膿や汗、虫刺されによる刺激でジクジクしやすくなります。冬場は空気の乾燥によって、かさついてしまい、刺激に弱くなり、痒みが強くなります。アトピーが冬場に悪化することが多いのは、このためです。
アトピー性皮膚炎の原因
アトピー性皮膚炎の増悪因子は人によって様々ですが、特に多いのがダニやハウスダストです。 血液検査で増悪因子を調べたり、アトピー性皮膚炎の活動性(病気の勢い)を調べることができます。 とくに乳児では、離乳食を始めるタイミングや食材の選定にも関わってきますので、血液検査をお勧めします。
アトピー性皮膚炎の治療
アレルギーテストの結果、アトピー性皮膚炎と食物アレルギーの関与があり、原因となる食物がはっきりし、除去する必要があると判断された場合は、その食物を除去するようにします。無闇な食事制限は栄養障害を招くリスクがありますので避けてください。
そして湿疹ができたら、塗り薬や飲み薬で良い状態に戻しましょう。
なお、アトピー性皮膚炎の治療にあたり、ステロイドの塗り薬に抵抗感をお持ちの保護者の方が少なくありませんので、ステロイド以外の治療法もご提示いたします。
ただし、ステロイドも症状に応じて必要な量を必要な期間だけ使い、症状が軽くなったら薬を減らしたり、弱いものに変えたりするように適切に用いれば、大きな心配はいりません。
気管支喘息
気管支に炎症が継続的に起こって様々な刺激に敏感になり、気管支を取り囲んでいる筋肉が収縮して空気の通り道が狭くなるアレルギー性の疾患です。気管支喘息は、日本では小児の5~7%、成人の3~5%くらいに認められ、その数は増える傾向にあると言われます。
乳幼児では、気管支炎に伴い、喘鳴を呈することがあります。
これは喘息性気管支炎と呼ばれ気管支周囲の筋の収縮よりはむしろ、気管支腔内の分泌物により物理的に気道が狭くなり、喘鳴を呈するものですので、気管支喘息とは区別されます。
気管支喘息の症状
気管支喘息では、せきや痰が出やすくなり、ゼーゼー、ヒューヒューという音(喘鳴)を伴って呼吸が苦しくなります。このような状態を「喘息発作」と言い、この発作の程度が強いほど、また頻度が多いほどに、気管支の炎症も強いことがわかります。
ひどくなると横になって眠れないほどになり、日常生活にも支障が出ます。
気管支喘息の治療
原因や悪化因子の除去・回避および薬物療法が、喘息治療の2本柱です。
気管支喘息の治療薬には、症状の無い時にも炎症を抑えるために使用する薬(コントローラー:長期管理薬)と、喘息発作時に症状を鎮めるために使用する薬(リリーバー:発作治療薬)があります。リリーバーを使わなくても済む状態を目指して、コントローラーを上手に使って治していきます。炎症をコントロールし、気道の炎症が無くなるまできちんと治療し、大人になっても喘息発作を引きずることのないようにすることが大切です。